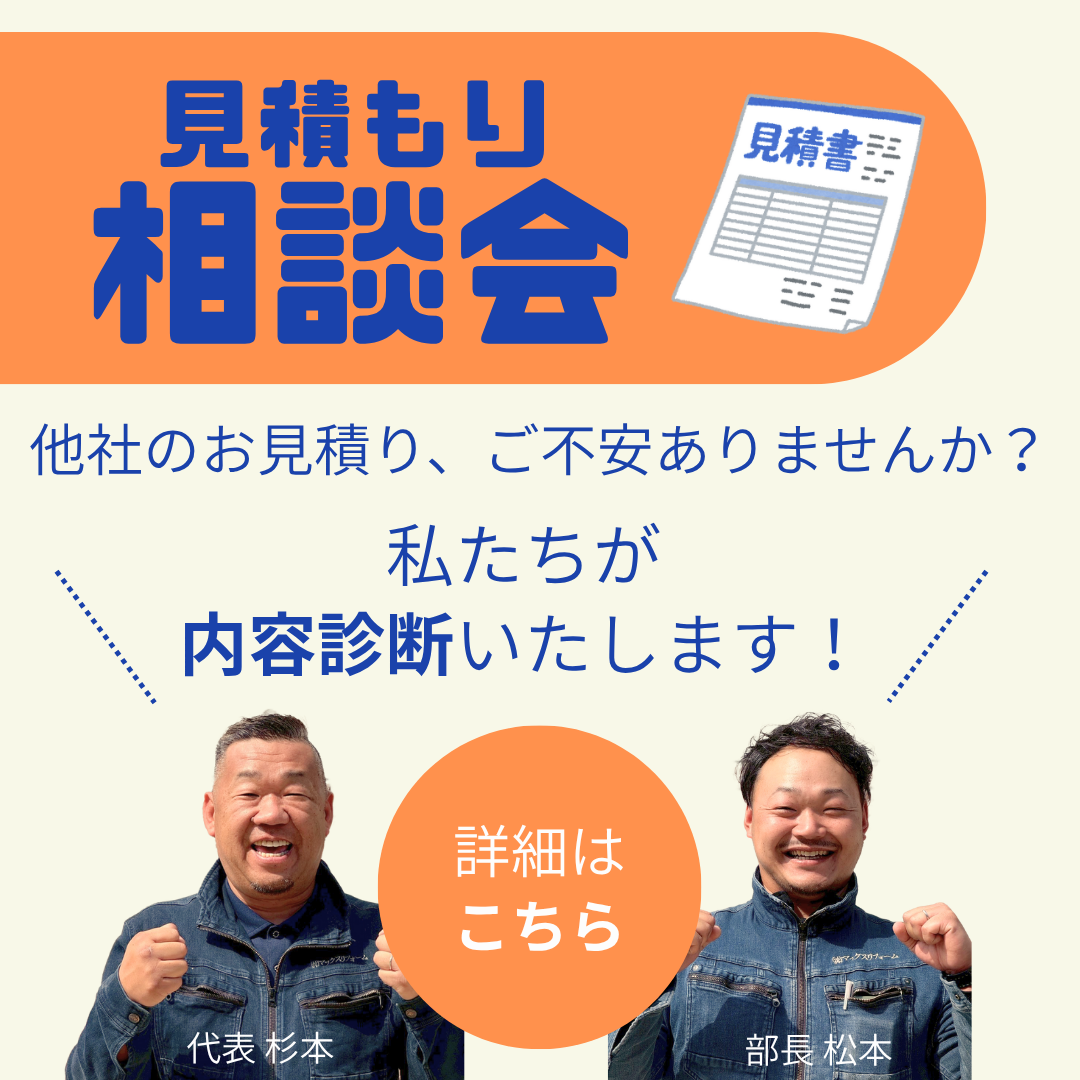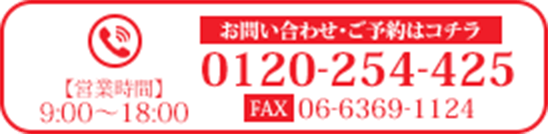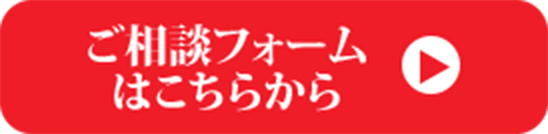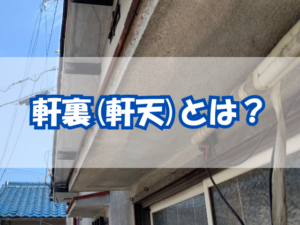棟瓦とは?よくあるトラブルと修理費用の相場を徹底解説!

日本の伝統的な建築には、独特の美しさと機能性を兼ね備えた「瓦屋根」が用いられます。
その中でも、屋根の頂部に位置する「棟(むね)」は、耐久性や防水性を高めるだけでなく、意匠的にも大きな役割を果たします。
棟瓦(むねがわら)とは?
棟瓦(むねがわら)とは、屋根の頂部や接合部に配置される瓦のことを指します。
屋根の構造を強化し、雨水の侵入を防ぐための重要な役割を果たし、主に以下のような目的で設置されます。
防水性の向上
雨水が棟部分から侵入するのを防ぐ。
耐風・耐震性の確保
屋根の構造を強化し、風や地震によるダメージを軽減。
美観の向上
伝統的な日本建築のデザインを際立たせる。
棟瓦にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる役割を持っています。適切な施工とメンテナンスを行うことで、屋根の耐久性を向上させ、美しさを長く保つことができます!
棟瓦の種類と特徴
大棟(おおむね)
屋根の最上部を水平に走る棟で、屋根のバランスを支える最も重要な部分です。装飾性の高い鬼瓦や熨斗瓦(のしがわら)を用いることが多く、耐久性と美観の両方を兼ね備えています。
隅棟(すみむね)
屋根の隅に設置される棟で、大棟と軒先をつなぐ役割を持ちます。風雨の影響を受けやすいため、特に強度が求められる部分です。
下り棟(くだりむね)
屋根の勾配に沿って大棟から軒先に向かって伸びる棟です。屋根全体の耐久性を高める役割を果たし、施工方法によっては独特のデザイン性を持たせることが可能です。
袖棟(そでむね)
屋根の端に取り付けられる棟で、風の影響を直接受けるため、しっかりと固定する必要があります。
棟瓦の構成と役割
冠瓦(かんむりがわら)
棟の最上部に配置される丸瓦で、雨水の侵入を防ぎながら屋根の美しさを引き締めます。
熨斗瓦(のしがわら)
棟の強度を高めるために積み重ねる薄い瓦で、雨水の流れを整え、耐久性を向上させる役割を担います。
鬼瓦(おにがわら)
棟の端に取り付けられる装飾瓦で、魔除けや家内安全の意味を持ちます。デザインは地域や家の格式によってさまざまです。
漆喰(しっくい)
瓦同士の隙間を埋めるために用いられる素材で、棟の強度を高め、雨水や風の侵入を防ぎます。
棟瓦によくあるトラブルは?原因と対処法
棟瓦は屋根の要となる部分ですが、経年劣化や自然環境の影響によりトラブルが発生することがあります。
以下では、よくある棟瓦のトラブルとその原因、適切な対処法について解説します。
1. 棟瓦のズレ・傾き
- 強風や地震の影響
- 経年劣化による固定力の低下
- 施工時の接着不良
対処法
- 定期的な点検を行い、ズレや傾きを早期に発見
- ずれた瓦は専門業者により正しい位置に戻し、固定し直す
- 耐震性の高い乾式工法へ変更することでズレを防止
2. 漆喰の剥がれ・ひび割れ
- 長年の風雨や紫外線による劣化
- 施工時の漆喰の厚さ不足
- 温度差による膨張・収縮の繰り返し
対処法
- 漆喰の剥がれが軽度であれば、部分的な塗り直し
- 大きな剥がれや広範囲の劣化がある場合は、漆喰の全面補修を実施
- 施工時に厚めの漆喰を施し、耐久性を向上させる
3. 葺き土の流出
- 長年の風雨により土が流出
- 動物の巣作りによる掘り返し
- 湿式工法の経年劣化
対処法
- 葺き土を新しく補充し、棟瓦を再固定
- 乾式工法に変更し、葺き土を使用しない施工へ切り替え
4. 鬼瓦のぐらつき・落下
- 風や地震の影響で接着部分が劣化
- 施工時の固定が不十分
- 経年劣化による接着材の剥がれ
対処法
- ぐらつきがある場合は、早急に固定を強化
- 落下の危険がある場合は撤去・交換を検討
- 耐震性を向上させるために金具固定を導入
5. 雨漏りの発生
- 棟瓦のズレやひび割れ
- 漆喰の剥がれによる隙間
- 瓦の接合部にできた小さな隙間からの浸水
対処法
- 雨漏りの原因となる部分を特定し、瓦や漆喰の補修を実施
- 防水シートの補強や、耐久性の高い材料への交換
- こまめな点検を行い、早期発見・早期対応を心がける
棟瓦のトラブルは、早めの対策をすることで被害を最小限に抑えることが可能です。
棟瓦は強風の影響を受けやすい部位。定期的な点検を行い、必要に応じて専門業者に相談するのがおすすめ!
棟瓦のメンテナンスと修理方法
棟瓦は屋根の中でも特に風雨や自然災害の影響を受けやすいため、定期的なメンテナンスが必要です。以下のような症状が見られた場合は、修理を検討しましょう。
- 棟瓦のズレや傾き
- 鬼瓦のぐらつき
- 漆喰の剥がれやひび割れ
- 葺き土の流出
- 雨漏りの発生
修理方法
- 棟瓦の積み直し:ズレや劣化した部分を修復し、耐久性を高めます。
- 漆喰の塗り直し:剥がれた漆喰を補修し、防水性能を回復させます。
- 棟の全面修理:大規模な劣化がある場合は、棟瓦をすべて撤去し、新たに施工します。
- 乾式工法への変更:地震や強風への耐性を向上させるため、より頑丈な施工方法へ切り替えることも可能です。
棟瓦の修理、費用相場はどれくらい?状況別で解説
棟瓦の修理費用は、状況によって異なります。ここでは、主な修理内容ごとの相場を紹介します。
1. 棟瓦の部分補修(5〜15万円)
適用ケース
- 漆喰の剥がれや小規模なズレの修正
- 一部の瓦が浮いている状態
ポイント
- 劣化が軽度の場合に適用
- 早期対応で修理費用を抑えられる
2. 棟瓦の積み直し(20〜50万円)
適用ケース
- 葺き土の流出が進み、瓦のズレが大きい場合
- 棟瓦全体の耐久性を回復したい場合
ポイント
- 一度棟瓦を取り外し、再施工する
- 耐震補強のために乾式工法へ変更することも可能
3. 棟瓦の全面交換(50〜100万円)
適用ケース
- 棟瓦の破損が広範囲に及ぶ場合
- 雨漏りが発生している場合
ポイント
- すべての棟瓦を新しく施工
- 長期的な耐久性を向上させる
4. 乾式工法への変更(30〜80万円)
適用ケース
- 耐震性を高めたい場合
- 軽量な屋根にしたい場合
ポイント
- 葺き土を使用せず、金具や接着剤で固定
- メンテナンス頻度が減るため長期的にコスト削減可能
5. 雨漏り修理(10〜30万円)
適用ケース
- 棟瓦の隙間から水が入り込んでいる場合
ポイント
- 原因箇所を特定し、適切な防水処理を施す
棟瓦の修理費用は、状態や施工方法によって大きく変わります。定期的な点検と早めの補修を行うことで、大規模な修理を避けることが可能です。
火災保険を活用した棟瓦修理

自然災害で棟瓦が損傷した場合、火災保険を活用して修理費用を補填できる場合があります。
適用範囲
- 台風や強風による棟瓦の破損
- 地震による棟瓦のズレ(地震保険加入時)
- 落下物による損傷
申請の流れ
- 被害の確認と記録:写真を撮影し、被害の程度を把握します。
- 保険会社に連絡:早めに報告し、必要書類を準備します。
- 鑑定人の調査:保険会社の調査員が現地確認を行います。
- 修理見積書の提出:専門業者に見積もりを依頼し、保険会社へ提出します。
- 保険金の受け取り:審査後、修理費用が支払われます。
災害に強い棟瓦「強力棟(防災棟)」とは?
近年、地震や台風などの自然災害が多発しており、瓦屋根の耐震性や耐風性が重要視されています。
従来の棟瓦に比べて高い強度を持つ「強力棟(防災棟)」は、そうした災害に強い屋根を実現するために開発された施工方法です。
耐震性の向上
従来の湿式工法(葺き土や漆喰を使用する工法)では、地震の揺れによって棟瓦がズレたり落下することがありました。
強力棟は、金具や専用の接着材を使用して瓦をしっかり固定するため、地震の揺れにも強い構造になっています。
耐風性の向上
強風による棟瓦の飛散を防ぐため、金具で瓦を一体化させ、風の影響を受けにくい設計になっています。
近年の台風による屋根被害の多発を受け、特に耐風性能が求められています。
メンテナンス頻度の軽減
漆喰や葺き土を使わず、長期的に劣化しにくい素材を採用することで、定期的な補修の必要性を減らします。
通常の棟瓦よりもメンテナンスの頻度が少なく、維持管理コストを抑えられます。
軽量化による建物への負担軽減
伝統的な湿式工法では、棟部分に大量の土や漆喰を使用するため、屋根全体が重くなりがちでした。
強力棟は、金具と接着剤を使用することで、棟の重量を軽減し、建物の負担を抑えます。
強力棟の施工方法
強力棟の施工には、次のような手順が含まれます。
棟木の固定
屋根の棟部分に専用の金具を取り付け、しっかりと固定します。
耐震・耐風用の接着材の使用
瓦の接合部分に強力な接着剤を使用し、ズレや飛散を防ぎます。
棟瓦の固定
金具やビスを使って棟瓦を固定し、強風や揺れに対する耐久性を向上させます。
仕上げ
防水処理を施し、仕上げのチェックを行った後、施工完了となります。
強力棟(防災棟)導入のメリット
- 地震や台風に強い屋根を実現できる
- 長寿命でメンテナンス費用が抑えられる
- 軽量化により、建物全体の耐震性が向上する
- 火災保険の適用対象になるケースが多い(自然災害での被害時)
強力棟は、特に地震や台風の被害が多い地域での屋根リフォームや新築工事におすすめの施工方法です。
既存の屋根に後付けで導入することも可能な場合があるため、現在の屋根の耐久性が気になる方は、専門業者に相談するとよいでしょう。
棟瓦に関するよくある質問
1. 棟瓦はどのくらいの頻度でメンテナンスが必要ですか?
一般的には5〜10年ごとに点検を行い、劣化の進行具合によって補修や交換を検討するのが理想です。台風や地震の後は特に注意しましょう。
2. 棟瓦がズレる原因は何ですか?
強風や地震、経年劣化による接着力の低下、施工不良などが原因となります。適切な固定方法を用いることで防ぐことができます。
3. 漆喰の剥がれを放置するとどうなりますか?
漆喰の剥がれを放置すると雨水が侵入し、屋根内部の劣化や雨漏りの原因になります。早めの補修をおすすめします。
4. 乾式工法と湿式工法の違いは?
湿式工法は葺き土や漆喰を使用する伝統的な方法で、乾式工法は金具や接着剤で固定する現代的な方法です。乾式工法は耐震性が高く、メンテナンスが容易です。
5. 棟瓦の修理費用はどれくらいかかりますか?
修理内容によりますが、部分補修なら5〜15万円、全面修理や積み直しの場合は30万円以上かかることもあります。
6. 棟瓦が落ちてしまった場合はどうすればよいですか?
すぐに専門業者へ相談し、修理を依頼しましょう。落ちた瓦を放置すると雨漏りの原因になります。
7. 火災保険で棟瓦の修理はできますか?
台風や地震などの自然災害による被害であれば、火災保険が適用される可能性があります。保険会社に確認してみましょう。
8. 棟瓦の補修はDIYでできますか?
専門的な技術が必要なため、DIYはおすすめできません。誤った施工をすると屋根全体の耐久性が損なわれる可能性があります。
9. 棟瓦の交換時におすすめの素材はありますか?
耐久性の高い陶器瓦や、軽量で耐震性に優れた瓦がおすすめです。最近では、防災瓦も人気があります。
10. 瓦屋根のリフォーム時に棟瓦も交換すべきですか?
屋根全体のリフォームを行う場合、棟瓦も一緒に交換することで耐久性が向上し、メンテナンスの手間を減らせます。
まとめ
棟瓦は屋根の耐久性を左右する重要な要素であり、定期的な点検と適切なメンテナンスが不可欠です。
特に、日本は自然災害が多いため、耐震・耐風対策を施した補強工事も重要になります。
瓦屋根の棟部分の状態が気になる方や、修理を検討されている方は、専門業者に相談し、適切なメンテナンス計画を立てましょう。
お問い合わせ
株式会社マックスリフォーム
公式サイト: https://maxreform.co.jp/
所在地:〒564-0053 大阪府吹田市江の木町5-24 フェスタ江坂401
- 電話番号:0120-254-425
- メールアドレス:info@maxreform.co.jp
- 公式LINE:LINEでお問い合わせ
- 予約カレンダー:こちらをクリック
- Zoom無料相談:予約はこちら
🏠 「瓦1枚からの交換OK!屋根のことなら何でもご相談ください!」